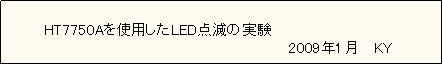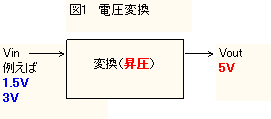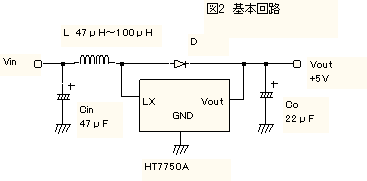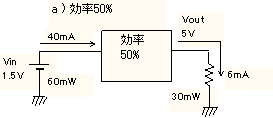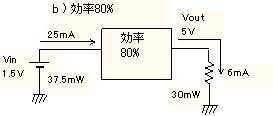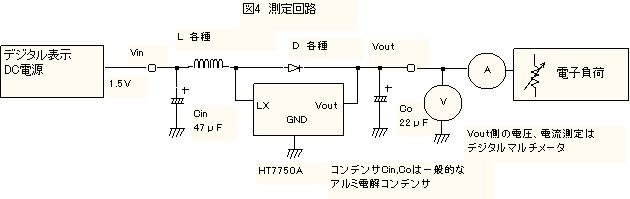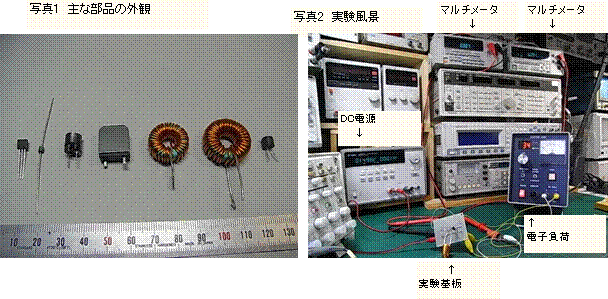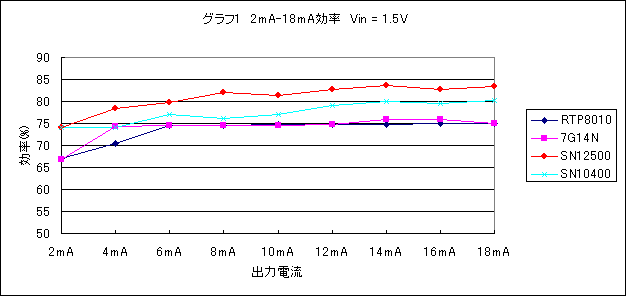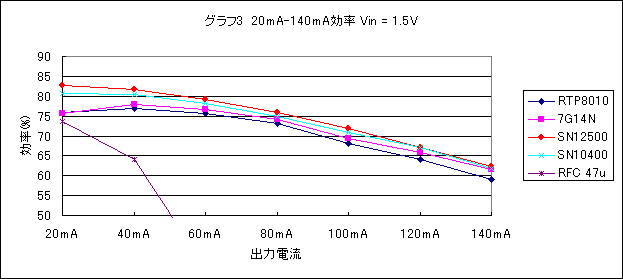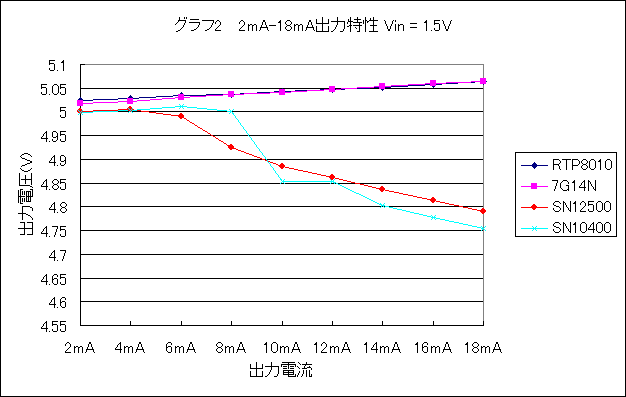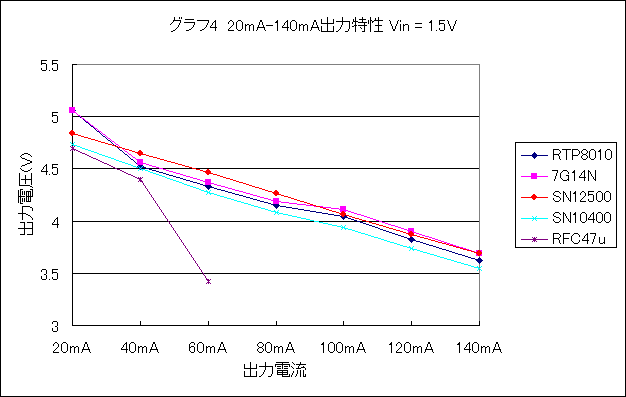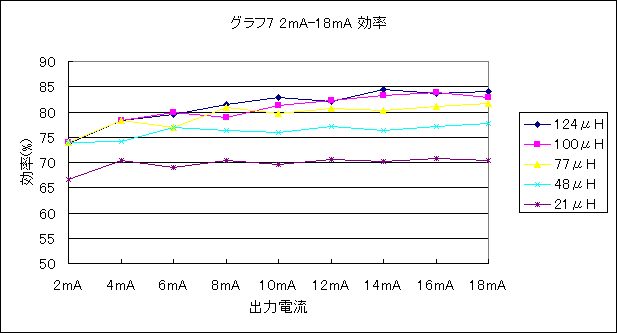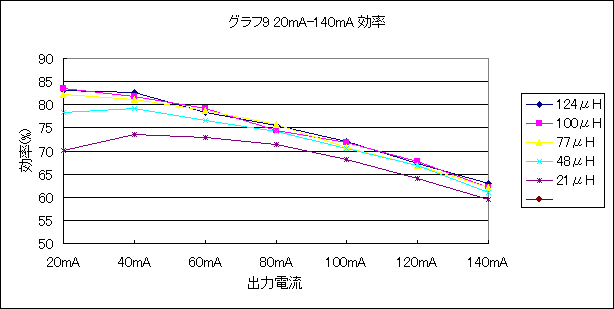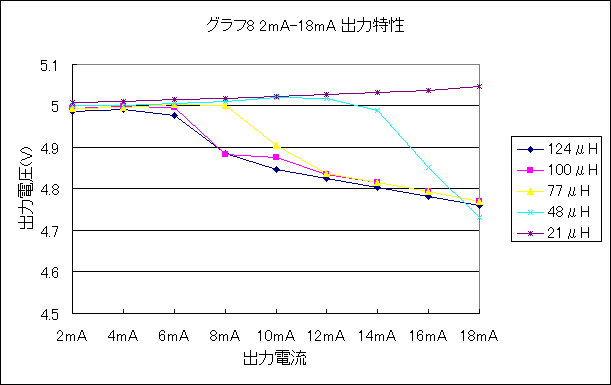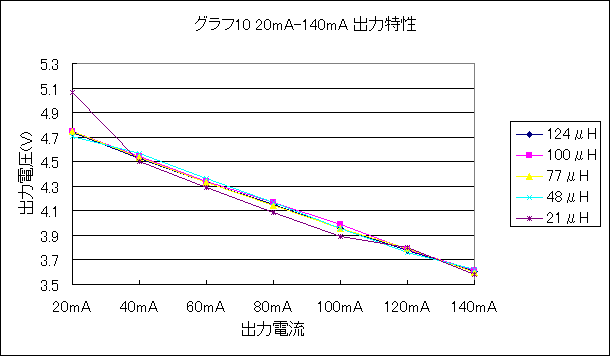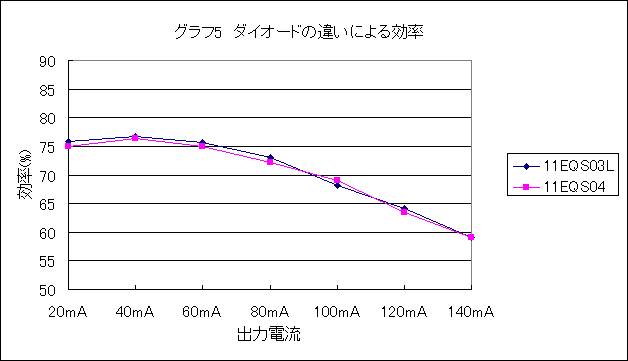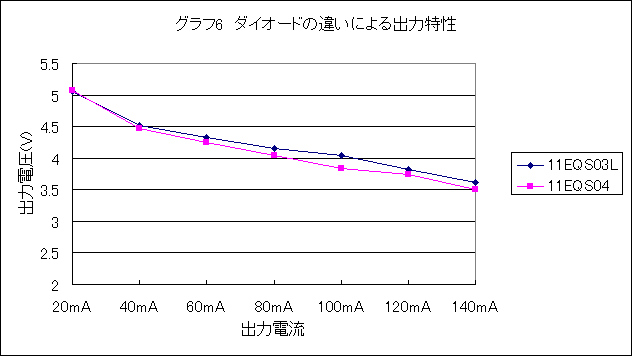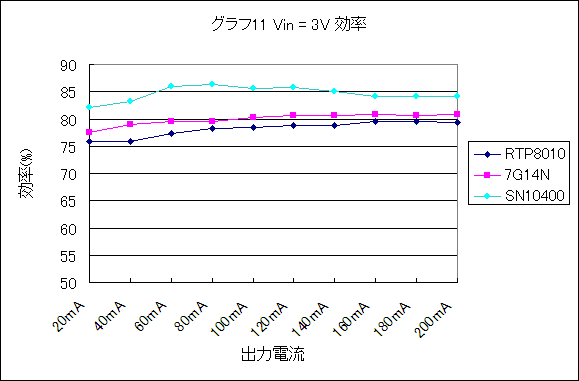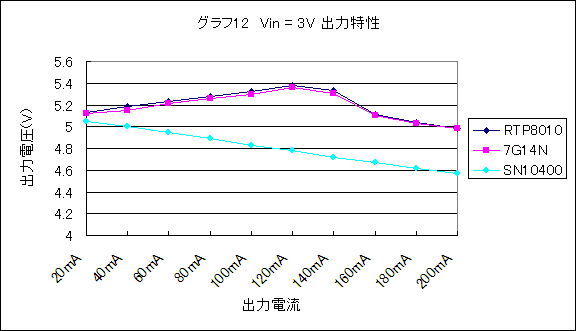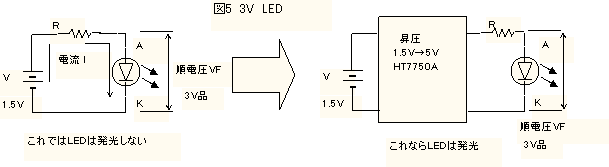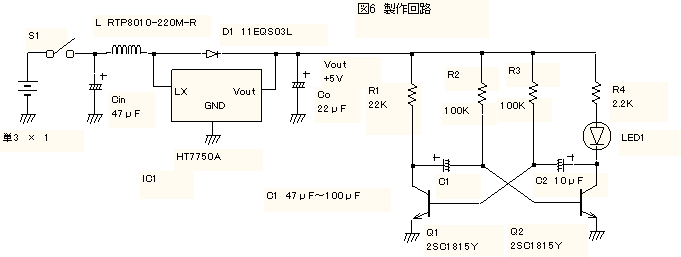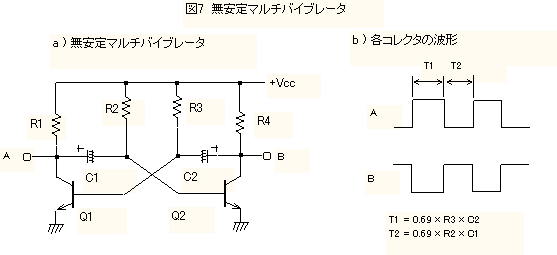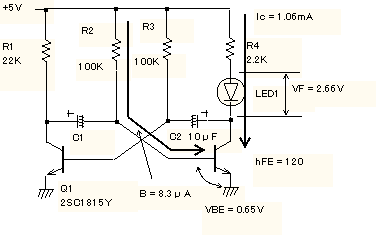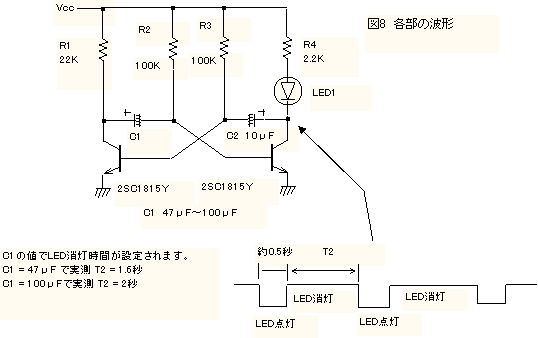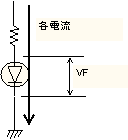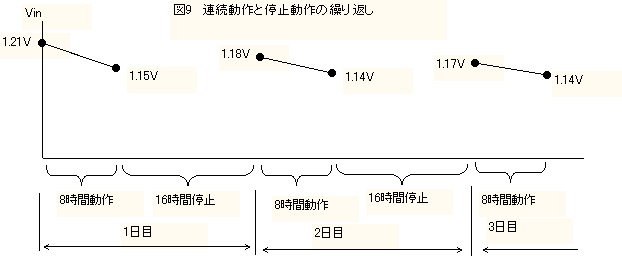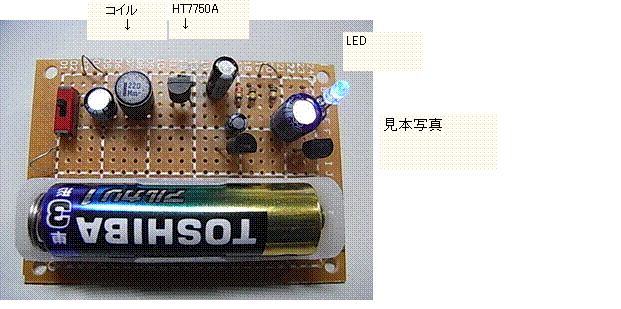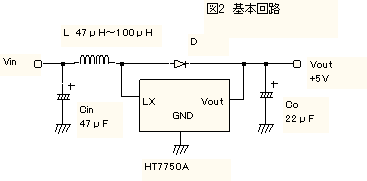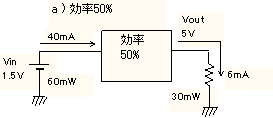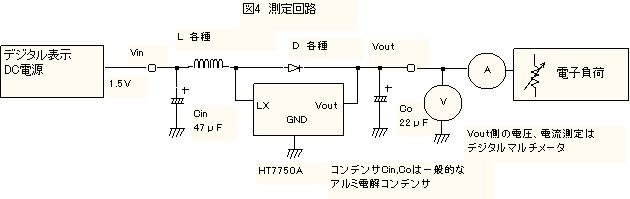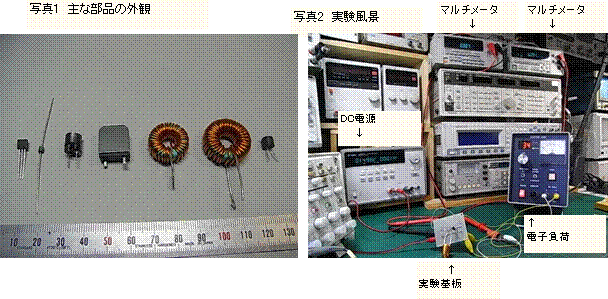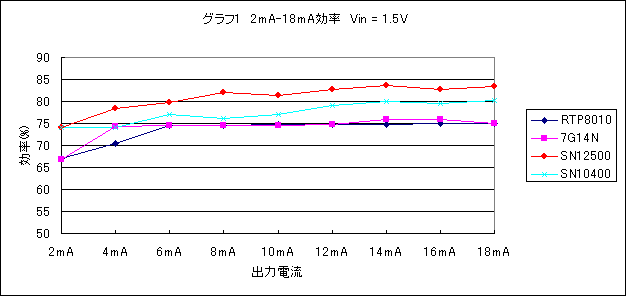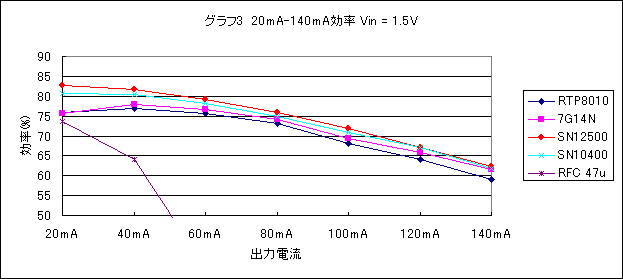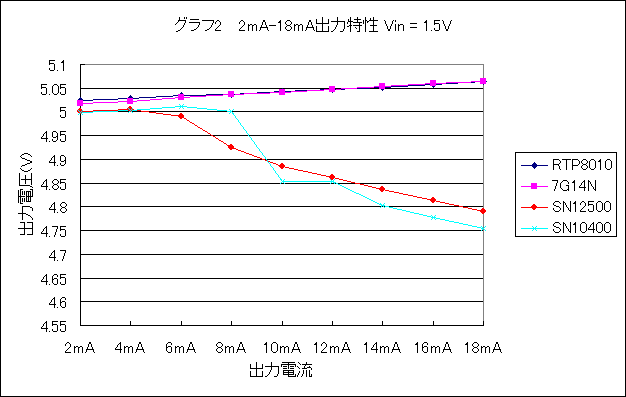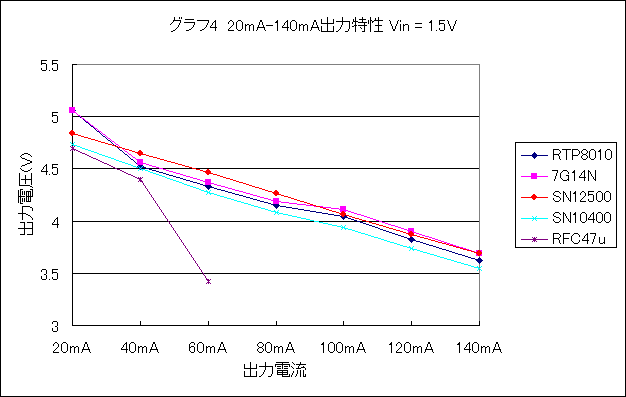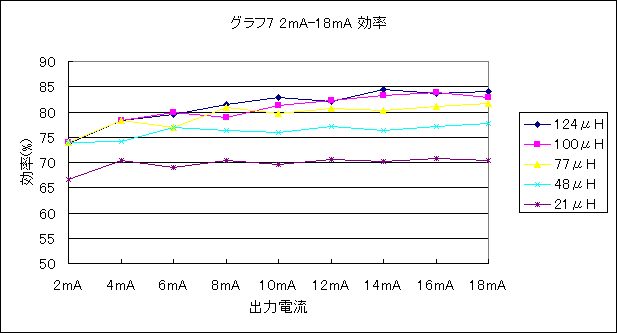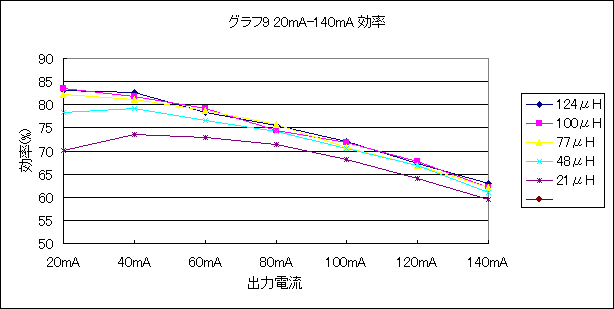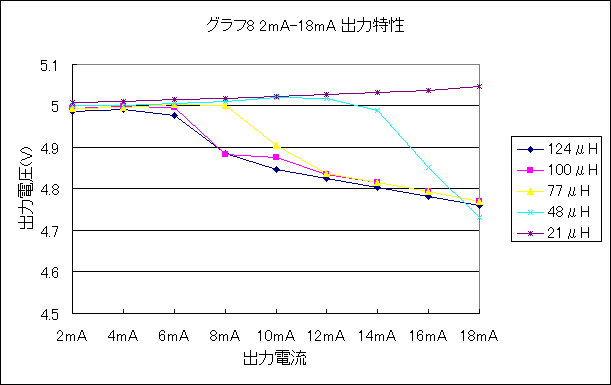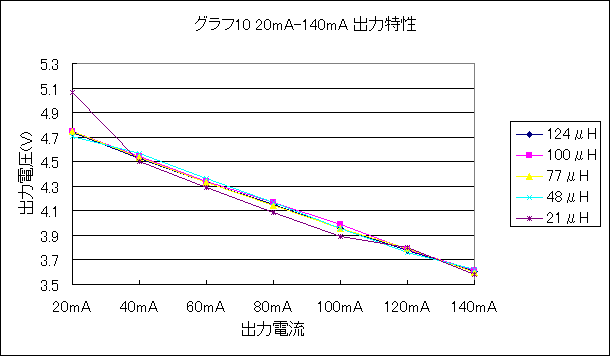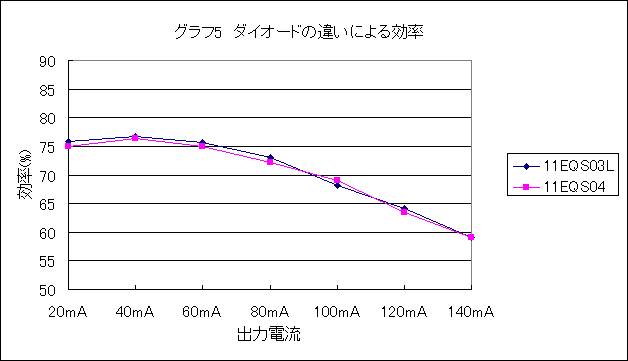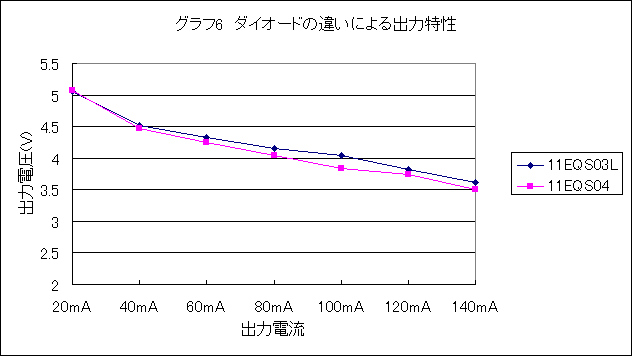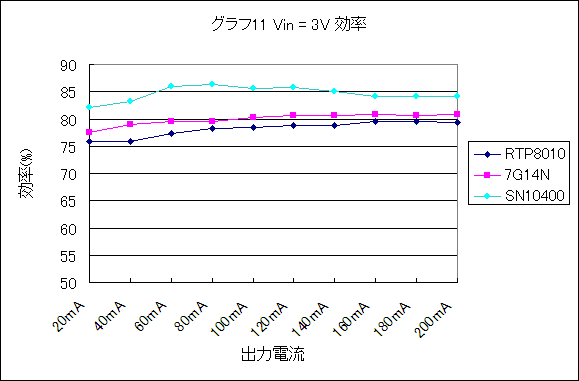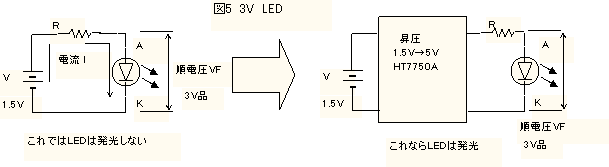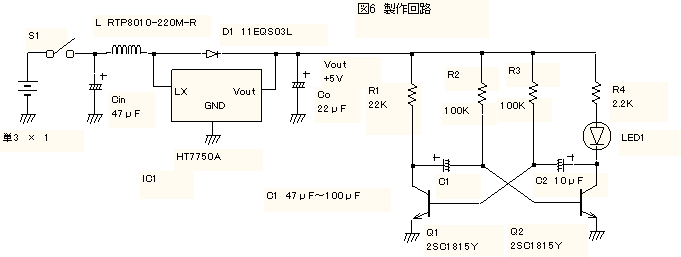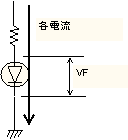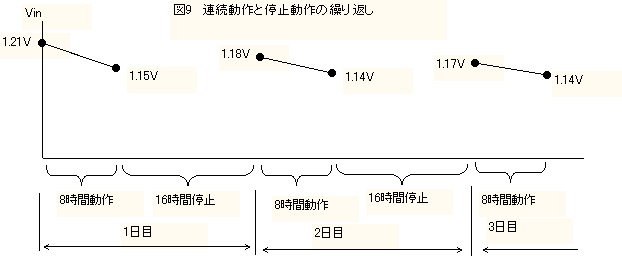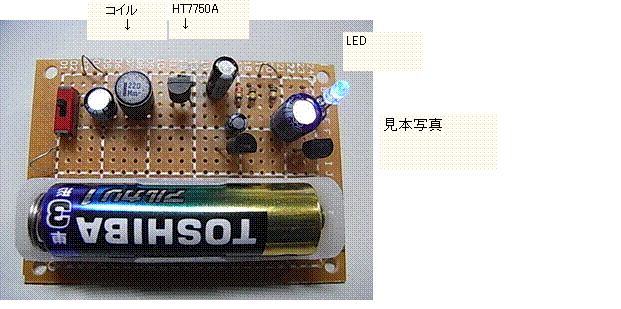|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.概要 |
|
|
|
|
|
ステップアップDC-DCコンバータIC
「HT7750A」を使ってみました。 |
|
|
|
このICは入力電圧を昇圧するICです。(図1) |
|
|
|
外付け部品が少なく、その基本回路を |
|
|
|
図2に示します。 |
|
|
|
今回使用したHT7750Aはパッケージが |
|
|
|
TO92の3本足で、出力は+5V固定です。 |
|
|
|
|
図2のようにコンデンサ2個、ダイオード1個 |
|
|
コイル(インダクタ)1個で構成出来ます。 |
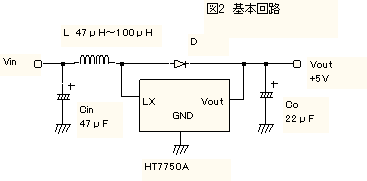
|
|
|
|
|
|
応用としては、例えば、1.5Vの乾電池を |
|
|
|
+5Vに変換してこれをセットの動作電圧 |
|
|
|
にすれば電池1本で5V動作 |
|
|
|
することが出来ます。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
主な仕様を以下に記します。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
・出力電圧誤差 ±2.5% |
|
|
|
|
|
・最大出力電流 200mA (Vin = 3V) |
|
|
|
|
・効率 85% (typ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
最大出力が200mAなのは魅力的です。 |
|
|
|
データシートによれば入力電圧Vinが3Vであれば、200mAの最大出力および効率85%となっています。 |
|
|
|
詳細はデータシートを参照願います。 |
|
|
|
|
|
|
| 2.実験の目的 |
|
|
|
|
|
このICを使って3Vを5Vに昇圧することは簡単と思います。 |
|
|
|
そこで、1.5Vを5Vに昇圧した場合の実験をしてみました。入力電圧が低いほうが |
|
|
|
効率が悪くなります。また、出力電圧も低くなってしまいます。 |
|
|
|
単3電池1本でどこまでこのICを使って動作するかの実験です。 |
|
|
|
|
|
|
|
予備知識として、前述の「効率」とは以下の意味です。 |
|
|
|
|
効率 = ( 出力電力 / 入力電力 ) × 100% |
|
|
|
つまり、入力で消費された電力と出力で消費された電力の比です。例えば、入力電力が100mW、 |
|
|
|
出力電力が70mWであれば、効率は70%です。 |
|
|
|
図3で考えてみます。出力Voutの消費電流を6mAとした場合、電力は P = V×I = 5×6mA=30mWです。 |
|
|
|
a ) のように効率が50%の場合のVin側の電力は30mWの2倍の60mWです。 |
|
|
|
この時の入力Vinの消費電流は I = P /V = 60mW / 1.5 =
40mA です。 |
|
|
|
これが b ) のように効率80%の場合はVinの消費電力は80%の逆数になりますので37.5mWとなり、 |
|
|
|
この時の入力Vinの消費電流は I = P /V = 37.5mW / 1.5 =
25mAとなります。 |
|
|
|
|
このように効率によって、Vin側で消費される電流が異なります。 |
|
|
|
|
|
|
|
図3 |
|
|
|
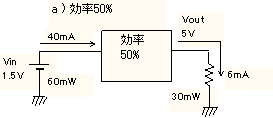
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.実験 |
|
|
|
|
|
図4に効率、出力電圧の測定回路を示します。 |
|
|
|
電子負荷は電子的に抵抗値を可変するもので、これによりVoutの出力電流を設定します。 |
|
|
|
電子負荷が無い場合は数ワットの定格電力の可変抵抗(ボリューム)でも良いです。 |
|
|
|
Vin側の電流測定は使用するデジタルマルチメータの電流レンジによる内部抵抗が高いと、 |
|
|
|
HT7750Aが起動しないかもしれません。今回はVinの電圧、電流はDC電源に内蔵のデジタル |
|
|
|
表示を直読して測定しています。 |
|
|
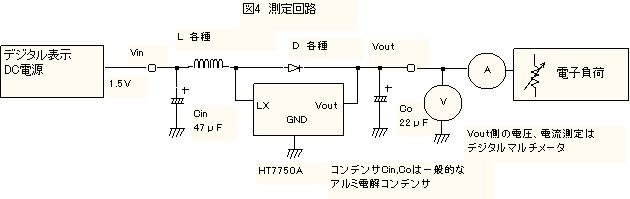
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
●使用部品 |
|
|
|
|
|
コンデンサCin,Coはデータシートの指定は「タンタルコンデンサ」です。 |
|
|
|
今回の測定は一般的な「アルミ電解コンデンサ」(汎用品)を使用しています。 |
|
|
|
なるべく、特殊な部品を使用したくない理由によるものです。ちなみに、タンタルコンデンサを使用 |
|
|
|
すると出力Voutのリップル成分の中で高い周波数成分(数MHzオーダー)は極端に減少しました。 |
|
|
|
コイルおよびダイオードは重要な部品です。この選択により効率が異なります。 |
|
|
|
写真1に主な部品の外観を示します。 |
|
|
|
|
|
(コイル) |
|
|
|
データシートで指定のコイルは入手が難しそうなので、手持ち部品の中からいくつか選んで |
|
|
|
実験します。インダクタンスの指定は47μH〜100μHですが、今回実験の部品の仕様を |
|
|
|
以下に示します。なお、数値は実測値です。 |
|
|
|
表1 |
|
|
|
メーカー |
|
型番 |
|
インダクタンス |
直流抵抗 |
|
|
|
|
サガミエレク |
|
RTP8010-220M-R |
23μH |
|
53.2mΩ |
|
|
|
|
サガミエレク |
|
7G14N-220M-RB |
22μH |
|
9.3mΩ |
|
|
|
|
NECトーキン |
|
SN12-500 |
|
124μH |
|
28mΩ |
|
|
|
|
NECトーキン |
|
SN10-400 |
|
78μH |
|
32.8mΩ |
|
|
|
|
不明 |
|
RFC 47u |
|
49μH |
|
1.41Ω |
|
|
|
|
|
|
RFC 47uは型番不明(一般的なマイクロインダクタ) |
|
|
|
|
|
直流抵抗は低いものが望ましいです。一般的なマイクロインダクタは直流抵抗が高いです。 |
|
|
|
今回実験の不明型番もマイクロインダクタですが、直流抵抗値が1.41Ω(1410mΩ)で他のコイル |
|
|
|
と比べると桁が異なります。他のコイルはすべてミリオーム単位です。 |
|
|
|
|
|
(ダイオード) |
|
|
|
ダイオードはデータシートでは「ショットキバリアダイオード」の1N5817が指定です。 |
|
|
|
このダイオードは「オン・セミコンダクタ−製」で順方向電圧VFは0.45V(Io=1A)です。 |
|
|
|
手持ち部品の中からこの特性に近いものを選び、以下に使用したダイオードを示します。 |
|
|
|
参考として「一般整流ダイオード」の1N4007も実験してみましたが、このダイオードでは動作 |
|
|
|
しなかったのでデータは取っていません。 |
|
|
|
表2 |
|
|
|
メーカー |
|
型番 |
|
順電圧VF |
|
内容 |
|
|
|
|
日本インター |
11EQS03L |
0.45V(1A) |
|
ショットキバリア |
|
|
|
日本インター |
11EQS04 |
|
0.55V(1A) |
|
ショットキバリア |
|
|
|
レクトロン |
|
1N4007 |
|
1.1V(1A) |
|
一般整流用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
       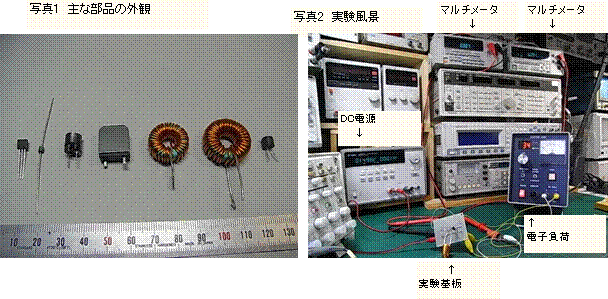
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
●実験結果 |
|
|
|
|
★1 効率 |
|
|
|
グラフ1、グラフ3に各出力電流における効率を示します。 |
|
|
|
ダイオードは「11EQS03L」とし、コイルを各種取り替えて測定したものです。 |
|
|
|
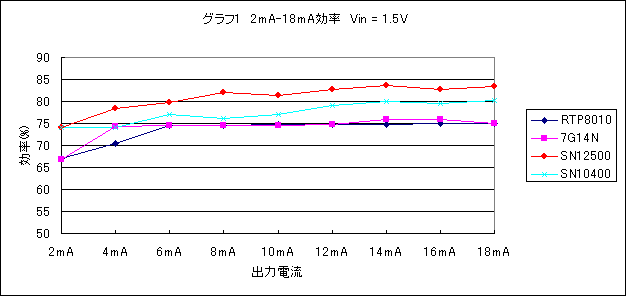
|
|
|
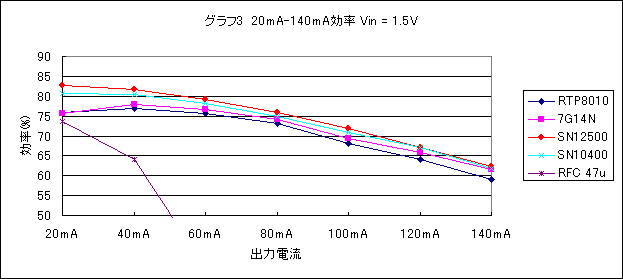
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
コイルにより効率がかなり違うのが分かります。 |
|
|
|
|
型番不明のRFC 47uは40mA以上では効率が極端に悪くなりますので、このコイルは |
|
|
|
使用不可と判断し、2mA-18mAのデータは残していません。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
★2 出力電圧 |
|
|
|
出力電圧特性をグラフ2,4に示します。 |
|
|
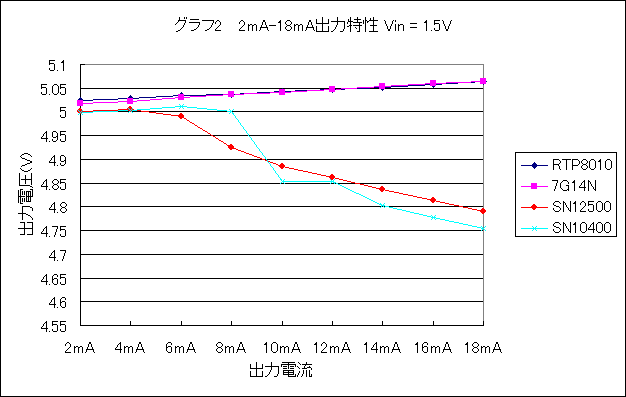
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
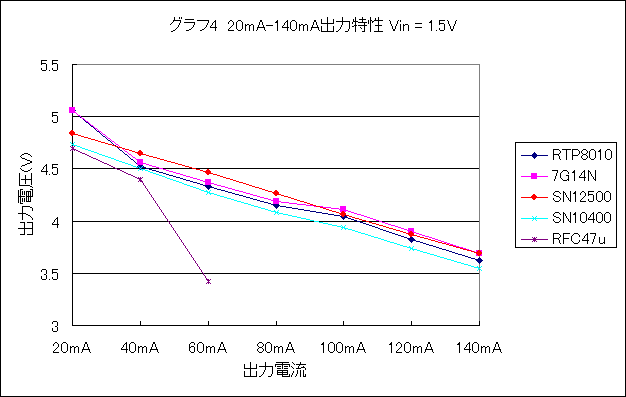
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
★3 インダクタンスによる違い |
|
|
|
|
|
|
同じコイルでインダクタンス値の違いについて実験しました。 |
|
|
|
手持ちのSN12シリーズがSN12500しかありませんでしたので、仕方なく、コイルの |
|
|
|
巻き数を減らしてインダクタンスを小さくして実験しています。 |
|
|
|
実測124μHの巻きを少なくしたインダクタンス値および直流抵抗は以下のとおりです。 |
|
|
|
|
インダクタンス |
直流抵抗 |
|
|
|
|
124μH |
|
28mΩ |
|
|
|
|
100μH |
|
26.8mΩ |
|
|
|
|
77μH |
|
24.8mΩ |
|
|
|
|
48μH |
|
20mΩ |
|
|
|
|
21μH |
|
12.8mΩ |
|
|
|
|
グラフ7,9に効率を、グラフ8,10に出力特性結果を示します。 |
|
|
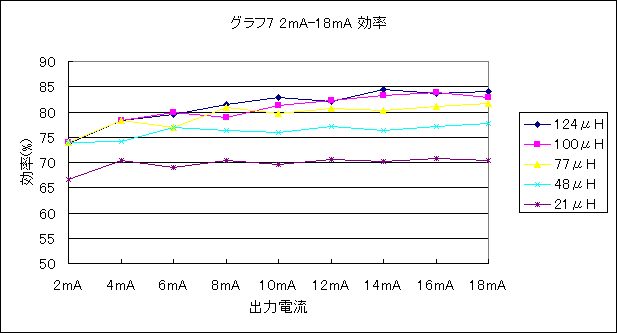
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
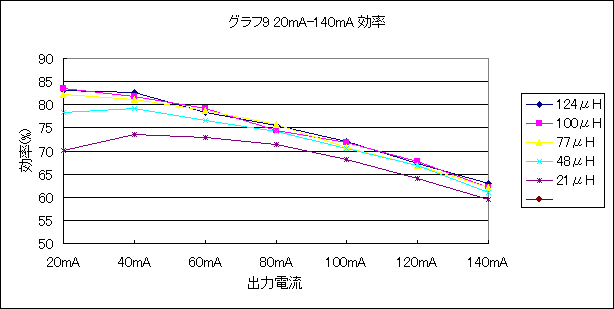
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
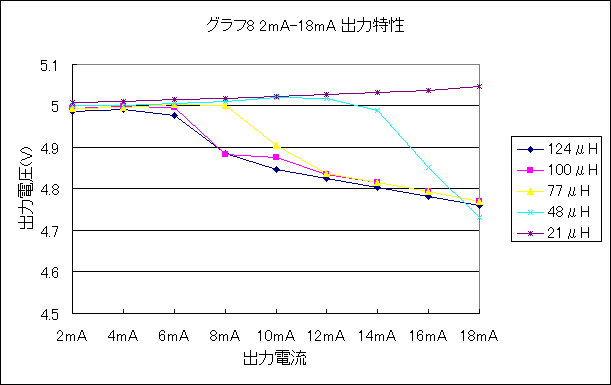
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
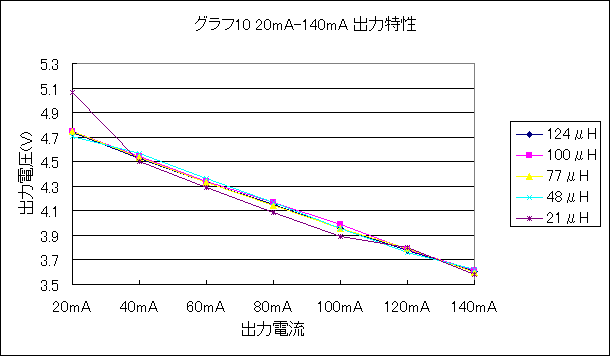
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
★4 ダイオードによる違い |
|
|
|
|
グラフ5,6にダイオードを交換した場合の効率および出力電圧を示します。 |
|
|
|
|
コイルは「RTP8010」です。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
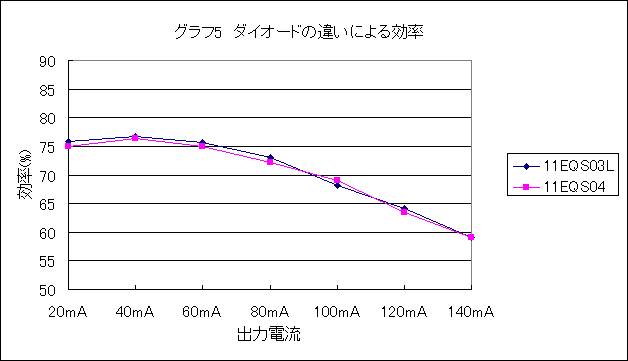
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
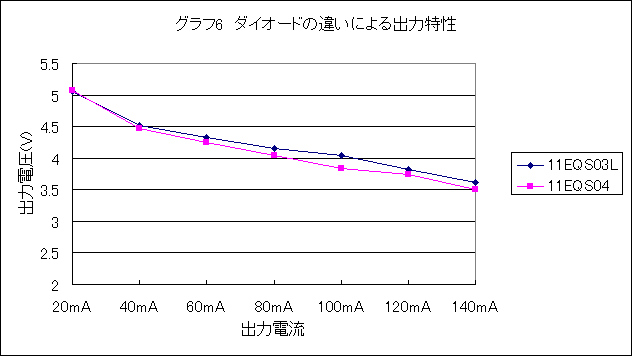
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
★5 Vin = 3V での実験データ |
|
|
|
|
|
|
|
参考として、Vin = 3V での実験データをグラフ11,12に示します。 |
|
|
|
|
SN12500は1.5V実験の時にコイルの巻き数を減らして、元に修復不能 |
|
|
|
|
となったのでデータはありません。(実験の段取りが悪いです) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
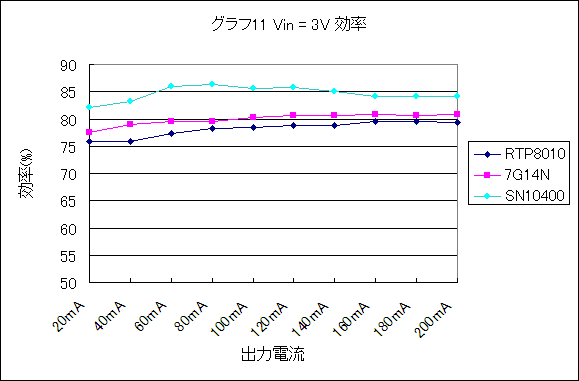
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.応用製作例 |
|
|
|
|
|
HT7750Aを応用した製作例として以下のものを製作しました。 |
|
|
|
|
|
(概要) |
|
|
|
|
|
単3電池1本を電源としたLED点滅回路。 |
|
|
|
LEDを点滅する製作は特別なものではありませんが、1.5V動作で青色LED等の順方向電圧の |
|
|
|
高いLEDを点滅(点灯)させようというものです。 |
|
|
|
青色LEDは順方向電圧が3V以上ですので、1.5Vでは動作しません。 |
|
|
|
|
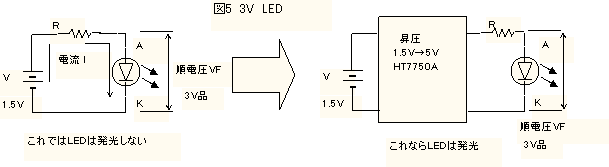
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
また、最大の目的は古くなった乾電池の再利用です。 |
|
|
|
|
筆者は乾電池のチェックは図6のような市販の「乾電池チェッカー」 |
|
|
|
を用いています。LEDが3個で乾電池の電圧に応じて |
|
|
|
点灯し、古くなったかを判断するものです。 |
|
|
|
緑色が点灯の場合は、「GOOD」で、黄色および赤色の順で |
|
|
|
電池電圧が減少していることを表示する仕組みです。 |
|
|
|
乾電池の電圧測定は電池の種類により、負荷抵抗を決めて、 |
|
|
|
ある程度の負荷電流が流れている状態で行います。 |
|
|
|
ちなみに、筆者所有の乾電池チェッカーの各色での電圧を |
|
|
|
測定すると、図6のとおりでした。 |
|
|
|
赤色の場合は電圧1.05Vですから、1.5Vに対して70%の |
|
|
|
電圧です。これにより、赤色点灯の状態が電池寿命と |
|
|
|
判断しています。(交換時期?) |
|
|
|
(注意:乾電池チェッカーは機種により、負荷抵抗および寿命の判断レベルが異なる |
|
|
|
かもしれません。図6は、あくまでも、参考値です) |
|
|
|
このようにチェックして赤色が点灯した場合に電池寿命と判断しているわけですが、電池電圧が70% |
|
|
|
近辺でも、これで動作するものを製作しようというわけです。 |
|
|
|
HT7750AはVinが1.2Vでも動作します。実験でも1.2Vおよび1.0Vでも動作しました。 |
|
|
|
ただし、これは出力電流が20mA以下のような小さい条件です。 |
|
|
|
したがって、電池が古くなっても、いかに、電池寿命が延びるかを考えた場合、電流を多く流さない |
|
|
|
ことです。 |
|
|
|
図6に製作回路を示します。 |
|
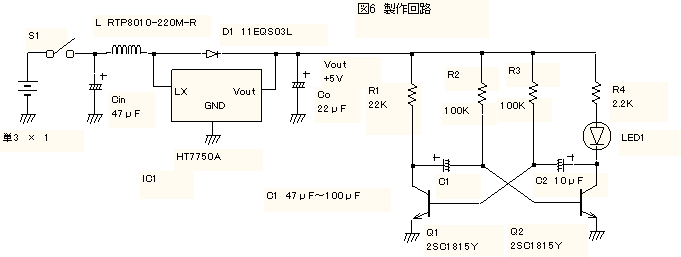
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LEDの点滅は「無安定マルチバイブレータ」を応用したものです。 |
|
|
この回路は図7のように自動的にパルスを発生します。各コレクタの波形は逆になり、その周期は |
|
|
|
抵抗とコンデンサの値により決まります。 |
|
|
|
今回のLED点滅はこの回路を応用し、コレクタにLEDを入れたものです。 |
|
|
|
つまり、コレクタが「L」の時にLEDが点灯します。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定数の求め方は次のようにします。 |
|
|
|
図7 定数の求め方 |
|
|
|
図7のように、まず、必要なコレクタ電流を |
|
|
|
決めます。コレクタ電流によりLEDは発光 |
|
|
しますので、使用するLEDで十分な明るさ |
|
|
となる電流を決めます。 |
|
|
|
ここでは、LEDの電流(コレクタ電流)を |
|
|
1mAとします。 |
|
|
|
抵抗R4は |
|
|
|
R4 = (Vcc-VF) / Ic |
|
|
です。ここで、VFはLEDの「順電圧」です。 |
|
|
VFの値はLEDにより異なり、今回使用の |
|
|
「青のLED」では約2.66Vです。 |
|
|
したがって、 |
|
|
|
R4 = (5V - 2.66V ) / 1mA = 2.34KΩ |
|
|
となり、E24系列の中から |
|
|
|
R4 = 2.2KΩ |
|
|
|
とします。R2はトランジスタが十分にONするための電流制限抵抗です。 |
|
|
|
必要なベース電流IBは |
|
|
|
IB = Ic / hFE |
|
|
|
です。hFEはトランジスタの「直流電流増幅率」で、この値はトランジスタにより異なり、 |
|
|
|
使用するトランジスタを2SC1815-Yとすれば、hFE =
120〜240 です。設計は最悪値の hFE = 120 |
|
|
|
で計算します。 |
|
|
|
|
IB = Ic / hFE = 1mA / 120
≒ 0.008mA |
|
|
|
となり、マージン(設計余裕)を見て、この値より大きくなるようにします。 |
|
|
|
マージンを考慮して、必要なIBの5倍とすれば、IB = 0.008×5 = 0.04mAですから、R2は |
|
|
|
R2 = (Vcc - VBE ) / IB =
(5 - 0.65) / 0.04mA = 108.75KΩ |
|
|
|
の計算結果です。これも、E24系列の中から |
|
|
|
R2 = 100KΩ |
|
|
|
としています。 |
|
|
|
コンデンサの値は |
|
|
|
0.69×C×R |
|
|
|
から計算しますが、最終的には点滅周期、時間は実測によりコンデンサ値を決定しました。 |
|
|
|
R1はLEDを接続しないので、この部分での消費電流を少なくする目的で、22Kにしています。 |
|
|
|
(R1の値を22KΩより高い抵抗値にすれば、さらに、LED-OFF時の消費電流が減少します) |
|
|
|
図8に実測値を示します。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LEDは流す電流値により、順方向電圧VFが異なりますが、参考として表3にVFの実測結果を示します。 |
|
|
|
設計上は各電流値に対応するVFの値で細かく設計する必要はありません。 |
|
|
|
例えば、表3の青色LEDであれば、5mA以下での設計値は VF = 2.8V としても良いです。 |
|
|
|
|
|
|
表3 VFの値 |
(条件:周囲温度 Ta = 20℃) |
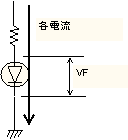
|
|
|
|
|
青 |
白 |
ピンク |
紫 |
|
|
|
電流値 |
BL304
2CA1A01 |
LLED-W501 |
LLED-F501 |
LLED-P501 |
|
|
|
0.5mA |
2.6V |
2.56V |
2.57V |
3.12V |
|
|
|
1mA |
2.66V |
2.6V |
2.62V |
3.23V |
|
|
|
2mA |
2.73V |
2.66V |
2.67V |
3.35V |
|
|
|
3mA |
2.78V |
2.71V |
2.71V |
3.43V |
|
|
|
|
4mA |
2.81V |
2.76V |
2.75V |
3.48V |
|
|
|
|
5mA |
2.84V |
2.8V |
2.78V |
3.53V |
|
|
|
|
|
注意:VFはLEDの型番で異なります。 |
|
|
|
筆者の個人的な感想ですが、表3の各LEDを使用した場合、 |
|
|
|
|
・青と白は0.5mA流せば十分な明るさです。2mA以上流すと眩しくてLED正面を |
|
|
|
|
見られません。特に、白は強烈な明るさ。 |
|
|
|
|
白を使用して「夜間用の目印灯」にすれば面白いかもしれません。 |
|
|
|
|
・ピンクと紫を初めて見ましたが、不思議な感覚です。 |
|
|
|
|
|
|
製作例では上記の青色LEDを使用しました。 |
|
|
|
コイルは、今回は「RTP8010-220M-R」を使用しています。 |
|
|
|
この理由は、このコイルの場合、ユニバーサル基板にそのまま搭載できることと、小型だからです。 |
|
|
|
結局、消費電流は乾電池部で、 |
|
|
|
|
LED消灯時 2mA |
|
|
|
|
LED点灯時 8mA |
|
|
|
です。LED消灯時間が短いほど電池寿命は延びます。 |
|
|
|
|
|
|
★ 実際に使用してみて |
|
|
|
|
|
出来上がったものを実際に使用してみました。乾電池は新品では無く前記の「乾電池チェッカー」で |
|
|
|
「そろそろ交換時期?」の赤LEDが点灯する使用済のアルカリ電池です。 |
|
|
|
この電池をLED点滅基板で動作した電源ON直後の値は1.21Vでした。乾電池チェッカーでは赤LEDが |
|
|
|
点灯する電圧は1.05Vです。この条件は乾電池チェッカー内部に乾電池への動作(消費)電流用として |
|
|
|
抵抗を内蔵しています。この値は10Ωくらいで(機種により異なります)、この条件での乾電池電圧を |
|
|
|
判断しています。したがって、LED点滅基板のように消費電流が数mAの場合は電圧値が高くなります。 |
|
|
|
実験は8時間の連続動作を行った後に16時間の停止(電源OFF)の繰り返しです。 |
|
|
|
連続動作のスタートと終了時に乾電池電圧を測定しました。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Voutは実験中では変化無く、5.004Vでした。このレポートでは合計56時間の範囲では |
|
|
|
問題無く動作し、あと何時間(何日)電池が使えるか楽しみです。 |
|
|
|
|
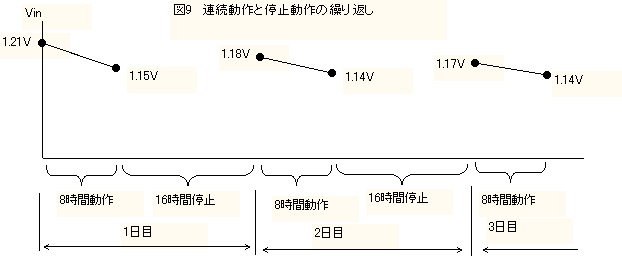
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
★ 部品表 |
|
|
|
|
|
表4に部品表を示します。LEDは表4の型番を使用しましたが、好みのLEDで良いです。 |
|
|
|
スイッチはなんでも良く、無くても良いです。(電池をホルダーから抜けば電源OFFです) |
|
|
|
電池ホルダーは「基板取付用」を使用しています。見本写真のように基板上にすべての部品が |
|
|
|
収まり、電池ホルダーも固定されて良いです。 |
|
|
|
|
|
表4 |
|
|
|
部品番号 |
内容 |
|
メーカー |
型番 |
|
備考 |
|
|
|
|
Cin |
ケミコン |
47μF |
|
|
|
耐圧16V以上 |
|
|
|
Co |
ケミコン |
22μF |
|
|
|
耐圧16V以上 |
|
|
|
C1 |
ケミコン |
100μF |
|
|
|
耐圧16V以上 |
|
|
|
C2 |
ケミコン |
10μF |
|
|
|
耐圧16V以上 |
|
|
|
D1 |
ダイオード |
|
日本インター |
11EQS03L |
ショットキ |
|
|
|
|
IC1 |
IC |
|
HOLTEK |
HT7750A |
|
|
|
|
|
|
|
|
L |
インダクタ |
|
サガミエレク |
RTP8010-220M-R |
|
|
|
|
|
|
|
LED1 |
LED |
Φ3 青 |
Linkman |
BL304B2CA1A01 |
好みのLEDで可 |
|
|
|
Q1,Q2 |
トランジスタ |
|
東芝 |
2SC1815Y |
|
|
|
|
|
R1 |
抵抗 |
22K |
|
|
|
カーボン |
|
|
|
|
R2,R3 |
抵抗 |
100K |
|
|
|
カーボン |
|
|
|
|
R4 |
抵抗 |
2.2K |
|
|
|
カーボン |
|
|
|
|
S1 |
スイッチ |
|
日開 |
SS-12SDP2 |
無くても可 |
|
|
|
|
XBATT |
電池ホルダ |
|
TAKACHI |
MP-3-1PC |
基板取付 |
|
|
|
|
PC1 |
基板 |
|
|
片面 ユニバーサル |
サイズ 47×72 |
|
|
|
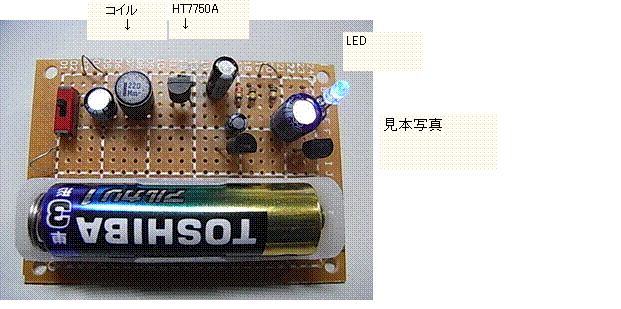
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|