【テスターの使い方 第5回目 導通チェック編】
テスターの購入はこちら
■テスタの使い方・第1回目 テスタの種類と特長編
■テスタの使い方・第2回目 パネルの表示文字の意味編
■テスタの使い方・第3回目 入力抵抗、実効値、平均値編
■テスタの使い方・第4回目 直流電圧と電流の測定編
■テスタの使い方・第5回目 導通チェック編
導通チェックは良く使うファンクションです。
◎準備
図28のように導通ファンクションに切り替えます。
導通ファンクションは他のファンクションと兼用になっている場合が多く、この例では「SELECTキー」によりさらに切り替えています。
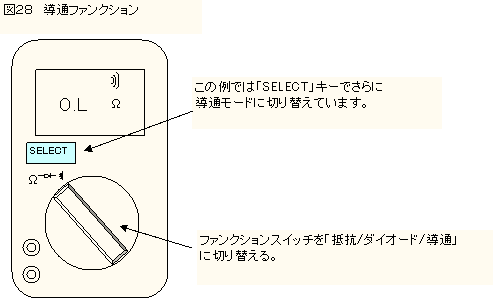
赤、黒のテストリードを差込、導通ファンクションになっているか、テストリードを当てて、ブザーが鳴るか確認します。
鳴らない場合は、他のファンクションになっていますので、「SELECTキー」を操作します。
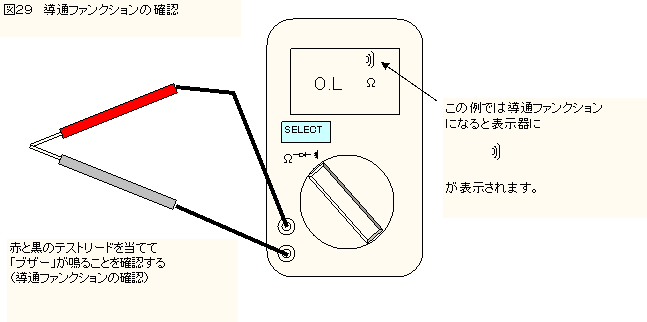
テスターの購入はこちら
◎導通抵抗の把握
導通はブザーの発音で確認しますが、「導通」と認識する抵抗値に範囲があります。
この範囲(発音)は機種により異なり、例えば
0Ω~85Ω
で発音し、この例では85Ωを越えると発音しません。
したがって、使用するデジタルテスタの発音仕様を一度、確認しておくことをお勧めします。
この仕様は取扱説明書に明記してあります。
また、テスタが導通を認識した場合はブザーの発音とともにその時の抵抗値を表示器に示します。
◎導通チェツクの実際
導通チェツクは「導通しているか」だけのチェックだけに用いるものではありません。
実際のチェックとしてコネクタの端子番号が分からない場合に、その判別法について1つの例を紹介します。
○スイッチ付ジャックの端子番号を判別する
図30にスイッチ付のモノラルジャックの回路シンボルを示します。
このジャックは図31のようにプラグが挿入されていない時は端子「T」と「SW」が接触(つまり、導通状態)しています。
プラグが挿入されると、今度は「T」と「SW」が離れ、「T」はプラグの「T」に接続されます。
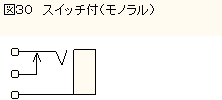
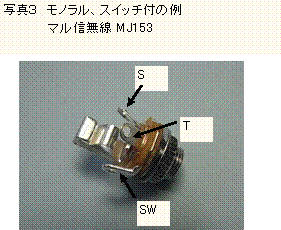
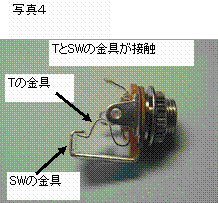
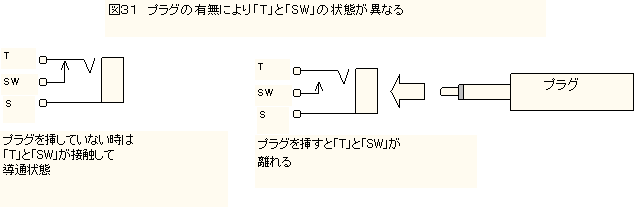
この端子番号は次のようにして判別することが出来ます。
①図32のようにプラグの「S」端子を判別します。(この場合、残ったもう1つの端子は「T」です)
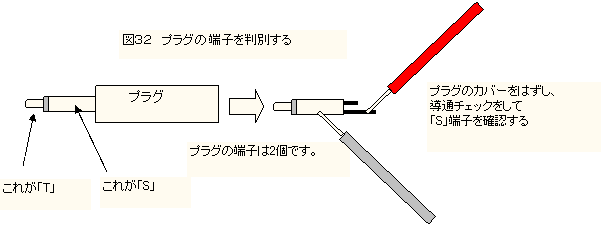
②図33のようにジャック側の「S」端子を判別します。
これによりジャックの残り2個の端子は「T」と「SW」です。
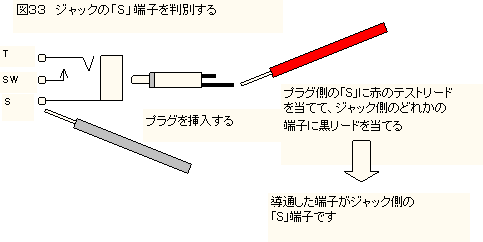
③図34のように残りの2個が「T」と「SW」であるか確認します。
この場合、プラグを外し、2個の端子間の導通チェックを行い、ブザーが発音するか確認します。
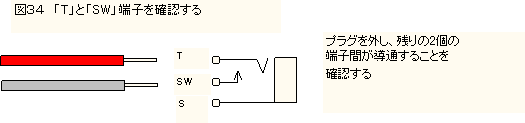
また、図35のようにプラグを挿入すればブザーが発音しません。
(つまり、プラグを挿入することにより「T」と「SW」が離れます)
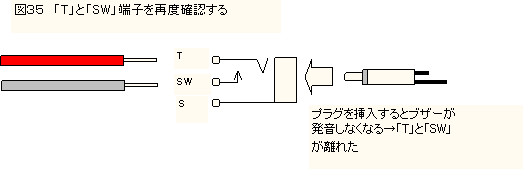
④図36のようにジャックの「T」端子を判別します。
プラグを挿入すればジャックの「SW」端子はどことも接触しません。
したがって、導通した端子がジャックの「T」端子です。
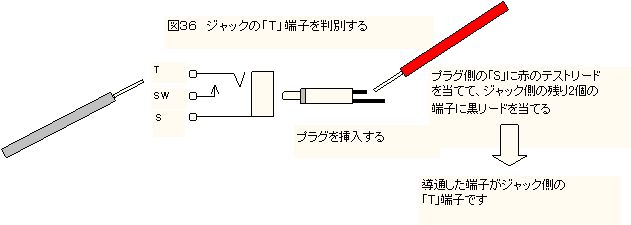
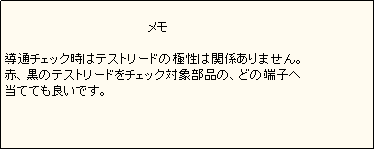
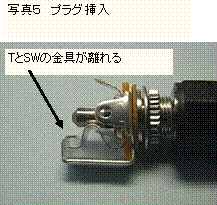
◎各種テストケーブルを利用して作業効率を上げる
テスタ付属のテストリードでは部品によっては当てにくい場合があります。
そのような場合、写真6に示すようなクリップアダプタを利用すると良いです。
このクリップアダプタはテストリードの先端に装着し、クリップアダプタの先端はこの例では「ICクリップ」になっています。
このようなクリップアダプタを利用することをお勧めします。
テスターの購入はこちら
■テスタの使い方・第1回目 テスタの種類と特長編
■テスタの使い方・第2回目 パネルの表示文字の意味編
■テスタの使い方・第3回目 入力抵抗、実効値、平均値編
■テスタの使い方・第4回目 直流電圧と電流の測定編
■テスタの使い方・第5回目 導通チェック編