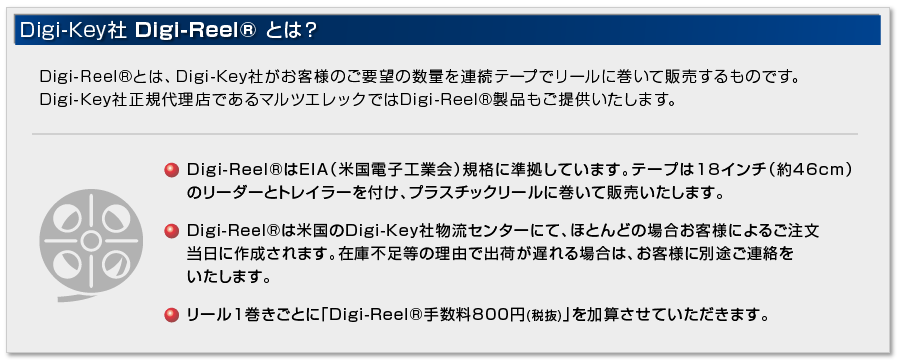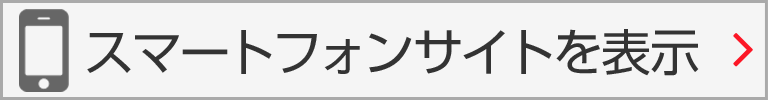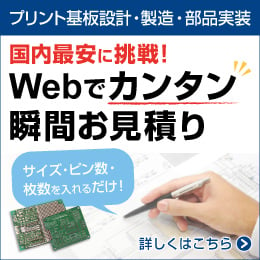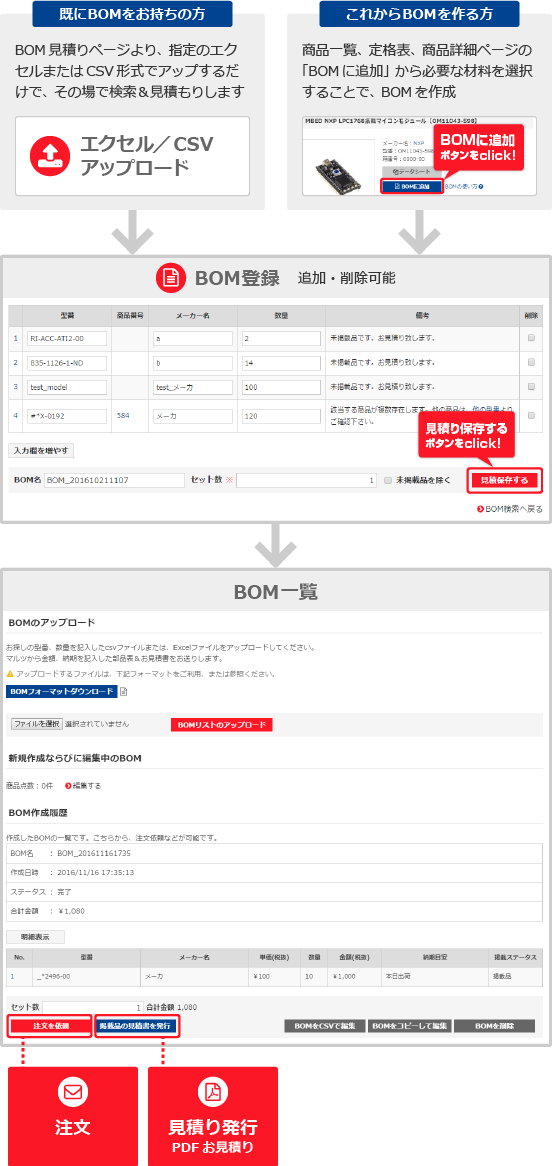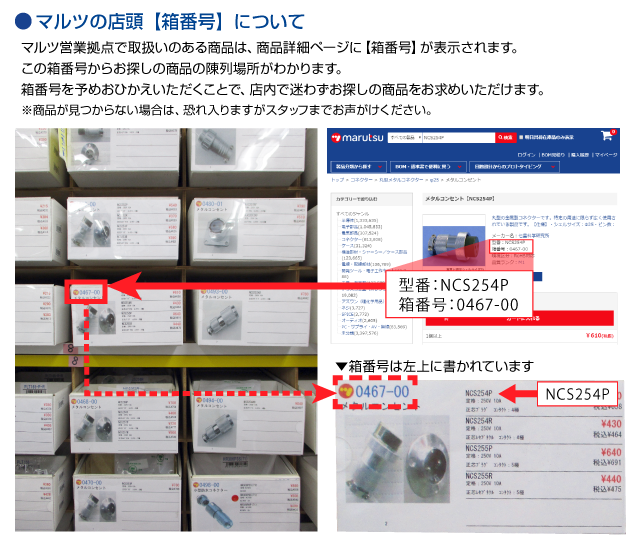センサなどを乗せた Conta 規格の小型基板(Conta モジュール)を接続できる RP2350A マイコンボードです。最大四つの Conta モジュールを接続できます。
※Conta 規格とは、breakout 基板の外形・コネクタ・信号配列などに一定の規約を設けることで、各基板間の相互接続性を確保するための規格です。Contaシリーズの全製品カタログはこちらからご覧いただけます。
RP2350A 周辺の構成は Raspberry Pi Pico 2 と機能互換があるので、Raspberry Pi Pico 2 + Raspberry Pi Pico用 Contaベースボード と同じ開発環境で開発できます。
Conta モジュールとマイコンボードは、I2C・SPI・アナログ入力/デジタル入出力(汎用IO)による接続が可能で、複数のモジュール、複数のインターフェースが共存可能です。
またマイコンボード上には 、Wi-Fi モジュール「ESP-WROOM-02」(シリアル接続)、「AQM1248A小型グラフィック液晶ボード」の接続コネクタ、5chのサーボ端子もあるので、はんだ付け無しで様々な機器を構築できます。
●仕様
・RP2350Aマイコン (※RP2350Aの機能は Raspberry Pi Pico 2 と同じです)
・フラッシュメモリ:4MB (32 Mbit)
・USB Type-C コネクタ搭載(USB 2.0)
・Conta モジュールコネクタ × 4
(M1~M4 のU字のコネクタ1組で1モジュール分です)
・Conta モジュールコネクタの 5 V ピンは USB-C 及び外部電源コネクタから供給
(外部電源で駆動した場合 5 V ピンの電圧は外部電源と同じ電圧になります)
・各 I/O ピンは 3.3V 駆動
・Wi-Fi モジュール「ESP-WROOM-02」搭載
(RP2350Aとはシリアル接続になります)
・AQM1248A小型グラフィック液晶ボード用接続コネクタ搭載
・5 ch のサーボ端子搭載
【内容物】
・1 × RP2350A マイコンボード基板
・8 × ナイロンスペーサー(M2 × 11 mm)
・8 × 鉄製ナベ小ネジ(M2 × 6 mm)
●※以下は配線パターンのみ(部品をハンダ付けすれば動きます)
・5 V入力用DCジャック(外径5.5 mm、内径2.1 mm) 搭載
・外部電源コネクタ装備(2.0 V ~ 5.5 V 入力可能)
コネクタ配置図

使い方
・M1 から M4 の Conta モジュールコネクタには様々なモジュールを同時に接続できます。
・各モジュールには2つの固定用ネジ穴が用意されていて、対応するベースボード側の取付け穴に固定できます。
・Conta モジュールコネクタは3グループのコネクタで成り立っています。
・コネクタ1 → I2Cコネクタ
・コネクタ2 → SPIコネクタ
・コネクタ3 → 汎用コネクタ

・I2C コネクタ、SPI コネクタ、拡張コネクタはそれぞれ独立しているので共存できます。
・3.3 V 信号系のモジュールのみ接続できます。
・5.0 V ピンは USB Type-C 及び外部電源コネクタから供給されます。外部電源で駆動した場合 、Conta の5.0 V ピンの電圧は外部電源と同じになります。
M1 から M4 の I2C コネクタについて
・基板全体で同一の I2C バスに接続されているので、M1 ~ M4 のコネクタは全て等価です。
・I2C 接続のモジュールを、最大4個まで同時に接続できます。(I2C アドレスがすべて違う場合)
・I2C バスは RP2350A の I2C_SCL(GPIO7/)I2C_SDA(GPIO6)と接続されています。
・各モジュールの IO4 ピンは、RP2350A の GPIO17(M1)、GPIO19(M2)、GPIO21(M3)、GPIO23(M4)に接続されてます。
・各モジュールの IO4 ピンは設定次第で PWM 出力になります。
M1 から M4 の SPIコネクタについて
・SPI 接続のモジュールは M1 ~ M4 のどこにも接続できます。
・SPI コネクタは 2つのグループに分かれていて、各グループにモジュールを1個接続できます。このため、マイコンボード全体で使える SPI 接続のモジュールは最大 2 個です。
・グループ1:M1とM3 がグループ1で、 RP2350Aの SPI1系の信号につながっています。SPI1_SCK はGPIO10、SPI1_MOSI はGPIO11、SPI1_MISO はGPIO12、SPI1_SS はGPIO13に接続されてます。
・グループ0:M2とM4 がグループ0で、RP2350Aの SPI0系の信号につながっています。SPI0_SCK はGPIO2、SPI0_MOSI はGPIO3、SPI0_MISO はGPIO4、SPI0_SS はGPIO5に接続されてます。
・よって、グループが異なる M1 と M2 や、M3 と M4 などは同時に接続できますが、M1 と M3 は同じグループ内なので同時には使えません。
・SPI1(グループ1)は液晶モジュールの接続とも信号を共有していますので、使用する場合には注意してください。
M1 からM4 の汎用コネクタについて
・M1 ~ M4 の IO1 はアナログ入力が可能です。基板全体では同時に 4 つのアナログ入力が取れます。
・M1 ~ M4 の IO1 はGPIOでもあるので、独立したデジタル入出力に設定もできます。
・M1 の IO1 ピンはGPIO26(AIN0)、M2 の IO1 ピンはGPIO27(AIN1)、M3 の IO1 ピンはGPIO28(AIN2)、M4 の IO1 ピンはGPIO29(AIN3)に接続されてます。
・汎用コネクタの IO2/IO3 はバスになっていて基板全体で RP2350Aと繋がっています。
・M1 ~ M4 の IO2 は共通の配線で、RP2350Aの UART0_RX(GPIO1)に接続されてます。
・M1 ~ M4 の IO3 は共通の配線で、RP2350Aの UART0_TX(GPIO0)に接続されてます。
・M1 ~ M4 の IO2/3 は基板裏のショートジャンパをカットすることで、モジュールの接続をバスから分離可能です。
Conta の5 V端子について
・5.0 V ピンは USB Type-C の VBUS(USB 5 V)、外部電源コネクタ(オプションの5 mmピッチコネクタ)に接続されてます。
・外部電源で駆動した場合 、Contaの5.0 V ピンの電圧は外部電源と同じ電圧になります。
Wi-Fi モジュールについて
・マイコンボード上にはESP-WROOM-02が搭載されていて、RP2350A とは全二重シリアルバスでクロス接続されています。
・シリアルバスは RP2350Aの UART1_TX(GPIO8)⇔ESP02 の RXD / UART1_RX(GPIO9)⇔ESP02 の TXD と接続されています。
・Wi-Fi モジュールを使わずに、システム全体の消費電力を下げたい場合には、Wi-Fi モジュールの電源を物理的に切り離すこともできます。
液晶ボード用接続コネクタについて
・マイコンボード上にはAQM1248A小型グラフィック液晶ボード用のコネクタがあり、液晶モジュールは GPIO と SPI 接続(SPI1)でコントロールされます。
・液晶コネクタの接続は、SCK 端子が SPI1_SCK(GPIO10)、SDI 端子が SPI1_MOSI(GPIO11)、CS 端子が SPI1_SS(GPIO13)、RS 端子が PWM4A( GPIO24) に接続されてます。
・液晶コネクタは Conta コネクタの SPI1 接続(グループ1)及び サーボ端子5とも信号を共有していますので、使用する場合には注意してください。
サーボ端子について
・マイコンボード上には、5 ch のサーボ端子が搭載されていて、最大で5ch のPWM出力が取り出せます。
・サーボ端子には RP2350A の PWM0A(GPIO16)、PWM1A(GPIO18)、PWM2A(GPIO20)、PWM3A(GPIO22)、PWM4A(GPIO24)が出力されます。
・サーボ端子5(GPIO24)は 液晶モジュールの接続とも信号を共有していますので、使用する場合には注意してください。
・サーボ端子の電源は 5 V 系で、外部電源の入力からダイオードを経由して接続されています。
電源供給について
・マイコンボードへの電源供給は、USB Type-C の VBUS(5.0 V のみ)、オプションの5mmピッチコネクタ(2.0 V ~ 5.5 V)から供給します。
・オプションの5 mmピッチコネクタには、コネクタやターミナルブロック、ケーブルなどをはんだ付けできます。
【資料】
・Conta 規格
・回路図(PDF)
・基板外形図